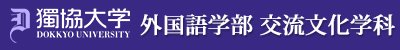2025/7/31 - DoTTS Faculty 教員コラム
暗黙知、科学知、陰謀論、そして反知性主義(北野収)
今、エアコンが効いた部屋から窓の外に広がる夏雲を眺め、この季節を「目で浴び」ながら、原稿を書いている。7月になると大学のキャンパスでニイニイゼミが鳴き始める。8月になるとアブラゼミやミンミンゼミがこれに替わり、9月になるとツクツクボウシに替わる。去年も、今年も、来年もこのことは変わらない。7月29日の朝、大学のキャンパスに足を踏み入れると、2~3年前から気になっていた異変を今年も「耳にする」こととなった(後述)。
1.科学知と暗黙知
大まかにいって、私たちの周囲あるいは内面にある知識には形式知・科学知(scientific knowledge)と経験知・暗黙知(tacit knowledge)があるとされる。私たちが「知識」と思っている知の大半は前者である。中世が終わり、科学と信仰が区別されるようになり、社会の世俗化が進み、資本主義と国民国家、その中での学校制度が発展すると、標準化された科学知以外の知は神話、伝説、迷信、ただの主観とされるようになった。近代的な知は、数値によって計測され定式化され、標準化された言語(方言でない「国語」や国際語としての英語)で語られる。
さて、現代において、暗黙知は先住民族や伝統的農民の専売特許なのだろうか。今は亡き明治生まれの祖父母、大正生まれの伯父伯母、昭和戦前生まれの両親の世代との語らいを思い出すと、彼/彼女らは部分的にではあるが、暗黙知の世界に片足を残したまま暮らしていたと思えるようになった。そして、昭和の高度経済成長期の東京で少年時代を過ごした私にも、暗黙知があると自覚するようになった。これも「老化」の一環なのだろうか。
2.経験の身体化という学び
都電やトロリーバスが走る新宿に生まれ、毎日、親に連れられて銭湯に通い、四畳半の部屋で白黒テレビをみていた幼年期。その後、雑木林と田畑と米軍基地・住宅しかなかった東京の北多摩地区(今では死語)で青少年時代を送った。春夏秋冬、日が暮れるまで、いや夜になっても、林や空き地に通い、田んぼの畦道を歩いた。夏には早起きしてセミの羽化(幼虫が成虫になること)を観察した。カブトムシ、クワガタはもちろん、トンボ、セミ、バッタ、コオロギ、アリ、カタツムリ、カエル等々とともに、いや、樹木や草花、土や石、森や風とともに育った。
夏の林と秋の林では、風に木がそよぐ音は違う。畦道で耳にする水の流れと、近所の用水路で耳にするそれとは音やテンポが違う。そのようなことを、理屈でなく身体で理解していたと思う。子どもの頃、愛読していた昆虫や植物の図鑑は科学知の産物だが、体験から身体的に得たものは、私にとっての暗黙知だったに違いない。幼かった私は「エコロジー」という言葉を知らなかったが、今思い起こすと生態系という概念を理屈でなく、身体で理解していたと思う。
3.陰謀論と科学的エビデンス
どちらも科学的根拠に乏しいとされることは似ていても、暗黙知と陰謀論は全く別の知識である。陰謀論を信奉するような態度を「反知性主義」と結びつけて批判することもある。しかし、多くの陰謀論は立派なエビデンスで「武装」し、もっともらしい既存の科学知を「論破」しようとする。例えば、「地球温暖化はフェイクである」という言説を信じている人が多くなってきた。もちろん反温暖化論者も、いろいろな科学的データで「武装」している。
4.元昆虫少年の「暗黙知」
50年以上前の小学生の頃、夏になると、当時、神奈川県の湯河原に住んでいた伯母のところに遊びに行った。そこでの楽しみの一つはセミの鳴き声を聞きながら歩くことだった。湯河原には東京にはいないクマゼミがいた。「シャンシャン」と鳴く黒い大型の南方系のセミである。愛読していた小学館と保育社の昆虫図鑑には「生息地の北限は神奈川県湯河原」と書かれてあった。「本当にその通りだ。やはり図鑑は凄い」と思った。近年(私の感覚ではこの2~3年)、湯河原から64km離れた埼玉県草加市のキャンパスでもクマゼミの鳴き声を耳にするようになった。冒頭で触れた「異変」とはこのことである。
半世紀の期間を経て、南方系のセミが北上したことは、何を意味するのだろうか。これを書きながら、以下のような声が聞こえる。「エビデンスを示さず、セミを地球温暖化に結びつけようとするオマエは反知性的だ」。農学者であり、社会科学者でもある私自身、「科学の子」の1人である。だから学会とか、公の場でこのような話をすることはできない。でも、「科学の子」であると同時に、「暗黙知の子」というもう1人の自分がいる。私は、「地球温暖化はフェイク」言説を垂れ流すユーチューバーでなく、元昆虫少年としての経験で培われた自分の中に宿る「暗黙知」を信じる。