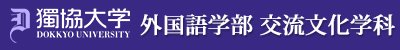2025/2/27 - DoTTS Faculty 教員コラム
タイ・メーホンソン紀行 2 (須永和博)
山がちな地形が広がるメーホンソンには、平地に暮らすシャンだけでなく、山地少数民族も多く居住しています。今回の調査の目的は、山地少数民族カレンの人々が最近始めたコーヒー生産の現状を調べることでした。
メーホンソン市内から4WDの車で未舗装の道を走ること3時間、目的地のフアイトンコー村(カレン語ではロラー村)に辿り着きました。この村では1999年以来、コミュニティ・ベースド・ツーリズム(CBT)と呼ばれる観光実践が行われています。大学院生時代、そのCBTの調査で長期滞在させてもらって以来、この村に通い続けています。
村の暮らしは、20年前から大きくは変わっていません。焼畑や水田で自給用作物を育て、森や川で狩猟採集や漁労を行い、食料の大半を自給する。これを基盤に、家畜飼育やツーリズムなど様々な現金収入手段を組み合わせ、複合的な生業を行なうのが基本的な生活スタイルです。

写真1: 高床式のカレンの家屋。

写真2:囲炉裏で調理

写真3: ある日の食事。

写真4: 収穫が終わった水田は牛の格好の放牧場所

写真5: 焼畑の風景。1月末〜2月初旬に伐採して乾燥させたのち、3月に火入れを行う。
こうしたカレンの暮らしは、危機に直面した時に高いレジリエンス(危機からの回復力)を発揮します。たとえば、コロナ禍では数ヶ月にわたって村を封鎖しましたが、暮らしに必要な食べ物の多くを周辺の田畑や森・川から得ていた彼らにとっては、村封鎖もさして大きな問題にはならなかったようです。自律的な生業が基盤にあることで、観光客の流れが一時的にストップしたところで、彼らの生存が脅かされることもなかったのです。
しかし、時代の流れとともに、こうした村の暮らしにも変化の兆しが見え始めています。若者の流出が止まらないのです。村には学校がなく、小学校は隣村に、中学校は市内の寄宿舎学校に行きます。近年では、大学進学する若者も多く、一度町に出ると村に戻ってきません。結果、カレンの生業の世代間継承が難しくなりつつあるのです。そのため、これまでの自律的な暮らしを維持ししつつも、若い世代が取り組める新たな生業創出が課題となっています。
こうしたなか、高等教育を受けた若者が中心になって、村の共有林にコーヒーを植え、それを共同で管理運営するプロジェクトを始めました。村のコモンズ(共有資源)として、新たなにコーヒー栽培を導入したのです。さらには、コーヒー豆を自ら焙煎し、直接販売するカフェも市内にオープンしました。彼らは、コーヒー栽培先進地域や有名バリスタとも関係を深め、そこから知識やノウハウを身につけることで、カフェ開業まで漕ぎ着けることができました。
カフェの名前は、村のカレン語名を冠したLola Gallery Dripです。コーヒーだけでなく、村の歴史や文化を紹介するギャラリーのような場所にしたい、そんな思いが込められています。店内にはコーヒーだけでなく草木染めの織物なども展示販売されています。また外装や内装も、カレンの伝統的な建築技法を用いています。

写真6: カフェ外観

写真7: 落ち着いた雰囲気の店内

写真8: ハンドドリップのコンテストで1位に輝いたスタッフ

写真9: 自家焙煎したコーヒー豆。ロゴも自分たちでデザイン。

写真10: 草木染めの布も展示販売
少数民族が栽培するコーヒー豆を、少数民族自身が運営する近隣都市のカフェで直接販売する。つまり彼らは、外部の仲買人を介さずに、エスニック・ネットワークの中で自律的にコーヒー生産・販売を行う手法を構築していると言えます。従来のフェアトレードが先進諸国のNGOや企業が支えるような事例が多かったのに対し、ローカルな範囲で生産から消費まで完結するカレンの人々の取り組みは「自治=自律的デザイン」(エスコバル 2024)という点においても興味深いです。とはいえ、この村のコーヒー栽培プロジェクトはまだまだ始まったばかり。継続して、その動向を見守っていきたいと思います。
前の記事
次の記事