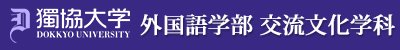2025/5/8 - DoTTS Faculty 教員コラム
両親と「うどん」が教えてくれたこと(北野収)
今は亡き両親の出身地は互いに離れていたが、共通点は雪国であったことだ。津軽出身の母の料理の味付けは濃く、しょっぱかった。関西文化圏の北限である富山出身の父はさぞ辛かったに違いない。二人の麵類の好みは大きく異なった。母は東日本のそば文化圏、父は西日本のうどん文化圏の人であった。
今でこそ、小麦粉のほとんどは輸入品だが、昔は、小麦はコメの裏作として広く作られていた。元々熱帯性の作物である稲は、品種改良が進む以前は、東北~北海道などの寒冷地には適しておらず、東日本ではソバやその他の雑穀も広く作られていた。
父はよく「うどんが食べたい」と口癖のように言った。だから、母もうどんを作ることもあった(現代では、このような書きぶりはジェンダー分業の観点から問題なことは承知しているが、昭和一桁の戦前世代の夫婦ということでご理解願いたい)。しかし、母が作ったうどん(暖かい麺の場合)の汁は、そばのそれと同じで、麺がほとんど見えない「真っ黒な汁」だった。だからだろうか、外食があまり好きでない父だったが、家にいる時でも「うどんを食べに行こう」と声をかけてきたり、一人でもふらっとうどん屋に行くことが多々あった。
今では考えられないことだが、1980年代頃までは、東京やおそらく東日本の店で出されるうどんの汁は母同様に「真っ黒」だった。関西人が「東京のうどんの汁は真っ黒」とよく揶揄していた。母のうどん汁が特殊だった訳ではない。
1980年の春、高校卒業を目前に私は中学校時代からの友だちと四国旅行に出かけた。岡山までどのように辿り着いたのかは覚えていない。岡山から国鉄の宇野線で宇野駅まで行って、そこから今は無き「宇高連絡船」に乗って高松に渡った。旅行のお楽しみの1つは、本場の讃岐うどんを食べることだった。
店で出されたうどんを見て私は驚いた。汁が「透明」(実際には薄い褐色)だったのだ。実は、当時、私はうどんの汁(色、味)がそばのそれとは異なることを知らなかった。何かの間違いだと思った私は、一生懸命醤油を足した。その醤油ですら色の薄い薄口醬油だった。暖かい麺にはたっぷり七味をかける主義の私は、四国でもそのようにした。しかし、口に入れた瞬間に飛びあがった。「辛すぎる」。店にあったのは七味ではなく、一味であった。このように、西日本と東日本では、調味料も違う。高校生だった私は何も知らなかった。
時は流れ、今では東京のうどんの汁も「透明」になった。
さて、つい先日、仕事で京都に行った際、京阪電車の乗り換え駅の立ち食いスタンドで昼食としてニシンそばを食べた。汁は東京のそばのそれとは違い、うどんと同じ「薄色」であった。不思議なことに、ニシンそばはうどん文化圏の関西ではどこにでもあるのに、そば文化圏の東日本では見かけない。食べ終わって、店の看板をみたら「うどん・そば屋」であった。関西では、駅の立ち食いの麺の店の多くは「うどん屋」「うどん・そば」と表記されている。東京では多くの場合「そば屋」である。どちらもそばもうどんも扱っているにもかかわらずだ。
些細なことではあるが、食におけるこのような地域ごとの多様性を大切にしたいと思う。
しかしながら、天邪鬼な私は、麺が見えない真っ黒な「東京のうどん」も懐かしく思うのである。