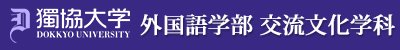2025/4/4 - DoTTS Faculty 教員コラム
大阪・釜ヶ崎への旅(須永和博)
1967年に出版された上野英信のルポ『地の底の笑い話』は、石炭から石油へのエネルギー転換を背景に衰退が進む九州・筑豊の炭鉱地帯を訪ね歩き、往時の炭鉱労働者の姿を描き出そうとした名著である。同書で上野が着目するのは、炭鉱労働者に共有されていた様々な「笑い話」である。たとえば、炭鉱での仕事をさぼる「スカブラ」と呼ばれる人たち。炭鉱労働者は手ぬぐいを首に掛けて仕事に臨むのが習慣で、仕事が終わると体も手ぬぐいも真っ黒になる。しかし、スカブラの手ぬぐいは真っ白のままだ。真っ黒な体と真っ白な手ぬぐいというコントラストが聞く者の笑いを誘う。
上野が炭鉱での「笑い話」を取り上げるのは、そこに「生活と労働のもっとも重い真実をそこに託している」からである (上野 1967: iv)。つまり、笑い話を掘り起こすことは、炭鉱労働者の歴史や思想を明らかにすることにもつながる、と上野は考えていた。スカブラも単なる怠け者ではない。「自由を獲得するための叡智」をもった「あこがれの象徴」であり、「抵抗と自由の精神」の象徴でもあるのである (上野 1967: 96-97)。上野には、消えゆく炭鉱労働者の小さき声を掬い上げ、彼らが育んだ遺産を後世に伝えようとする切実な思いがあったという(水溜 2022: 74)。
上野が炭鉱を訪ね歩いた1960年代以降、失業した炭鉱労働者が向かった先の一つが「寄せ場」であった。寄せ場とは、主に建設現場で働く日雇い労働者が求職活動を行う場所のことである。東京の山谷、横浜の寿町、大阪の釜ヶ崎が「三大寄せ場」として知られてきた。高度経済成長を背景に建設現場の労働力需要が高まるなか、閉山した炭鉱から多くの労働者が寄せ場に流入したのである。それゆえ、寄せ場の労働世界で育まれた精神文化・政治文化には、炭鉱と共通する側面も多いという (原口 2022: 257-260)。
私のゼミでは、毎年3月に釜ヶ崎を訪れている。今年でもう13年目だ。高度経済成長という時代を底辺から支えてきた人たちが、寄せ場で生み出した文化やセーフティネットには、貧困や孤立が深刻化する現代社会を乗り越えるヒントがあると思うからだ。しかし、かつて日雇い労働者で溢れていた釜ヶ崎も、高齢化や求人方法の変化に伴い、寄せ場機能は大幅に縮小している。最近は、労働者に代わって安宿を求めてやってくる外国人観光客の姿の方が目立つくらいだ。こうしたなか、かつての釜ヶ崎を知る人たちが中心になって、日雇い労働者として生きてきた人々の声を掬い、その記憶を紡いでいこうとする取り組みも行われている。彼らの活動(memory work)に触れることもまた、釜ヶ崎訪問の目的である。寄せ場としての記憶を継承しようと奮闘する人たちの姿は、四半世紀以上前の上野と重なる。
大阪合宿の拠点とするのは、アートNPO「こえとことばとこころの部屋」(ココルーム)が運営するゲストハウスである。詩人の上田假奈代さんが代表をつとめるココルームは、アートや表現を介して釜ヶ崎の記憶を伝える活動を長年行ってきた。そこで私たちは、ココルームの活動を見聞きし、時には実際に参加しながら、アートや表現のもつ意味や可能性について考える。

写真1: 商店街にあるゲストハウス。入り口では毎日バザーが行われている。

写真2: 1階のカフェスペース。
たとえばココルームの庭には、井戸がある。この井戸は、ココルームが主宰する表現プログラム「釜ヶ崎芸術大学」の一環としてつくられたものである。長年建設労働に従事してきたおじさんたちの技術や知恵を頼りに井戸を掘ることで、釜ヶ崎に生きる/生きたひとたちの経験や記憶を感じ取ってもらうという試みである。完成までのべ700人が参加したそうだ。井戸掘りが始まると、次第に子どもたちは元日雇い労働者のおじさんたちを「先生」と呼ぶようになり、すると今まで自分のことをあまり語らなかったおじさんたちも、過去の経験を少しずつ語るようになったという。共に体を動かすという経験を通じて、新たな関係が生まれていったのである。

写真3: 庭に掘られた井戸
ゲストハウスには、釜ヶ崎芸術大学の一環として制作された作品が随所に展示されている。たとえば、先日私が泊まった「銀河鉄道の駅」と名づけられた部屋には、ココルームの常連だった元日雇い労働者のおじさんの作品が所狭しと飾られていた。ゲストハウスに飾られてた釜ヶ崎のおじさんたちの作品を見ていると、「日雇い労働者」という集合的な存在としてではなく、1人ひとりの人生が浮かび上がってくる。言い換えれば、アートや表現は、紋切り型の表現からは溢れ落ちてしまう個別具体的な生のあり方を映し出す。

写真4: 「銀河鉄道の駅」に飾られている作品

写真4: ゲストハウスに飾られている作品

写真5: スーパー玉出のチラシを撚ってつくられた通天閣など
いま私たちの身の回りには、様々な差別や偏見が蔓延っている。差別や偏見は、他者を紋切り型の表現に押し込め、顔の見えない存在にすることで生まれるものだ。釜ヶ崎で行われているアートや表現活動には、こうした状況を打開し、より良い社会を創造していくためのヒントがあるのではないか。そんな思いや希望を抱きながら、大阪でのゼミ合宿を続けている。
【引用文献】
上野英信1967『地の底の笑い話』岩波書店.
原口剛2022「流民のカルトグラフィ─筑豊から釜ヶ崎への回路」『現代思想』50(13): 253-262.
水溜真由美2022「炭鉱労働者の精神文化に対するまなざし」『現代思想』50(13): 73-93.