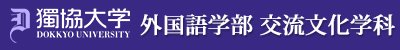2025/3/25 - DoTTS Faculty 教員コラム
経済成長で変わるもの、変わらないもの(北野収)
久しぶりに東南アジアをフィールドにした社会学者の村井吉敬先生の本(『小さな民からの発想』)を読み直していたら、現場で話をしたインドネシア人の青年の発言に関連して、次のような下りが目に入った。「同じ人間が、同じ会社で汗を流して働きながら、一方が途方もなく高い給料をとるということは、[…]「差別」としか映っていない」。ふと、タイ出身の友人とそのご家族のことを思い出した。
妻の親友にタイ出身の女性(Aさん)がいる。Aさんは私たち夫婦と同世代で、ご両親はタイで事業を営んでいた。きょうだい・親戚には医者が複数いる。タイの大学でコンピューターの勉強をしたAさんは、若い頃、タイIBMに勤務していた。その後、Aさんはアメリカの大学院に留学して、コンピューターとビジネス(MBA)の2つの修士号を取得した。知り合ってさほど月日が経っていない頃、妻と彼女はこんな話をした。「日本IBMのお給料はどのぐらいなの」。妻は「たぶん、大体〇〇ぐらいじゃないかな」とあてずっぽうで答えた。バブル崩壊後とはいえ、日本がまだ世界の経済大国として君臨していた1990年代前半の話だ。すると、Aさんは「同じ会社で、それは不公平だ」とムッとしたという。大学出たての若手社員の給料どうしで比べて、その差は倍以上あった。同じ仕事をしても、国が変われば給与水準は異なる。多くの場合、本国社員あるいはグローバル採用された人と、現地採用の人も給与水準が異なる。
ニューヨークに住んでいた頃、Aさんとのつながりで、タイ人と交流する機会が多かった。主観だが、皆、素朴で人懐こい感じがした。タイ人会のパーティーに飛び入りで参加させてもらったこともあった。大人たちが、歌ったり、踊ったり、素朴なゲームをして、子どものように喜んでいる様子をみた妻と私は「日本人のパーティーじゃ絶対にこんなのあり得ない」と顔を見合わせた。でも、とても懐かしく楽しい時間を過ごしたことを覚えている。
あれから、30年の歳月が流れた。Aさんは、不幸なことにアメリカ人の旦那さんには先立たれたが、アメリカで立ち上げたタイレストラン・チェーンのオーナー経営者として手腕を振るっている。現在のAさん家族は、英語とタイ語を駆使して、アメリカとタイの二拠点で、家族や甥・姪が行き来をしているトランスナショナル・ファミリーだ。往来の途中で、時には日本にも立ち寄ってくれる。家族・親戚のつながりとネットワークの強みが、ビジネスでも、子どもや孫の学業面でも、大きな強みになっている。今ではAさんだけでなく、息子さんたち、Aさんの親戚やきょうだいを含めて、わが家とは家族ぐるみのお付き合いをさせていただいている。タイのGDPはいまだに日本のそれに及ばないが、大企業の管理職の給与水準に限定すれば、タイの水準は日本のそれを既に上回ったと聞く。おそらくタイ社会では富裕層に属し、アメリカ社会でもそれなりの成功を収めたAさんたちの生活水準は、わが家のそれよりも、確実に、というよりは遥かに上であることは認めざるを得ない。
Aさん家族との交流を踏まえて何が言いたいか、そろそろ書いておこう。かつて私は、経済・物質的に豊かになれば、共同体や家族の助け合いは減少し個人主義化していくものと考えていた…、日本人の多くがそうなったように…。あるいは、脱宗教化(世俗化)していくものだとも思っていた。Aさんたちは、非常に熱心な仏教徒である。「時間差」はあれど、少なくとも東・東南アジアの少なからぬ国々の中で、物質的豊かさを伴った経済的発展が進行していくとしても、精神・文化面が経済・物質面と同期的に画一化・個人化されていく訳ではないのかもしれない。Aさん家族と私たちの違いは何か。信仰?それもあるかもしれないが、それだけではないかもしれない。
各種の経済統計が示しているように、そう遠くない将来、インド、ブラジルはもちろんのこと、マレーシア、インドネシア、メキシコ等がGDPのランキングで日本よりも上位にくることになる。経済・物質面の成長が、精神・文化面の変化と対応していないとすれば、好むと好まざると、私たちは「失ってきたもの」に向き合わざるを得なくなる時がやってくるかもしれない。もちろん、たった一家族の情緒的な印象をもちだして、それを日本人全体と比較するのはナイーブすぎるし、科学的でないとするご批判があることは承知している。



前の記事
次の記事